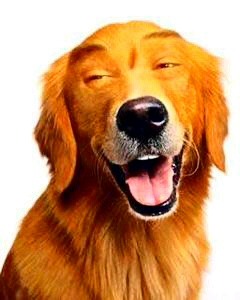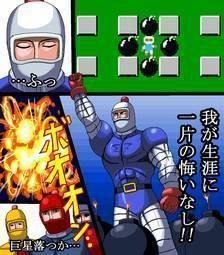詠泉さんとモバ友になろう!
日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!
-
- 2018/1/17 20:14
- 【雑節】土用とは?
-
- コメント(2)
- 閲覧(12)
-

-
- 1月16日のニュース について:
- 今日は、土用に付いて講釈して見ましょう…。
φ(..)
さて、此の土用と謂う言葉ですが一般的には、夏土用の丑の日が有名ですが此は俗説の土用丑の日に【う】の付く物を食べると其の季節は、息災だと言う事に由来します。
お話しを戻しますが此の土用とは、どの樣な意味が有るかと言いますと暦では、土用は、立春、立夏、立秋、立冬(総じて四立)の前日(節分)迄の約18日間に配される期間で季節の変わり目を意味します。
先程も触れましたが節分も春のみに有らず【四立】の前日は、全て節分に当り現在は、春の節分の行事が残って居ます。
お話しを戻しましすが日本は、基本的に四季に恵まれて居る為、暦では、一年を四分割として各季節を割当てて居りますが其の季節毎に気【季節や方位の神(八将軍)】が存在して居ると考えられて居ました。
其の思想が陰陽五行で平安時代に唐より伝来し暦を司る陰陽師によって広められました。
さて各季節の五行とは、春→木気、夏→火気、秋→金気、冬→水気と成ります。
此の四気を総じて司るのが土気(併せて九星将軍)と成りますが其の理由は、土中には、上記の四気が存在し木→種子、火→地熱、金→鉱物、水→水脈が存在します。
故に全てを内包する大地信仰と共に土公神と呼ばれる神が発生し其の神が活発化する時期(用→働き=土気が働く)土用とされました。
此の土公神の役割は、四気を司る為、各季節をも司り季節の変わり目には、各季節の気を相剋すると信じられて居ました。φ(._.)
故に土公神の活発化する土用の時期は、土弄りや穴堀、殺生等は、忌み嫌われて居ました。
話が遡りますが夏の盛り(旧六月)の丑の日は、【一粒万倍日】とされ吉日とされた為、土用の丑の日に丑に肖り【う】の付く物を食べると土公神の力と相まって息災と成ると信じられた訳です。
要するに医療の発達して居ない時代の切実な願いが暦の習わしと成る訳です。φ(._.)メモメモ